
AIが進化するとWebライターの失業率は高まりますか?

AIの進化は確かにWebライター業界に影響を与える可能性があります。
紙媒体に記事を書くライター業は、インターネットの発達と共にWeb媒体に活動の場を広げました。今はクラウドソーシングの躍進によって、Webライターと呼ばれる職業名が一般的になっています。

ところが近年、AIの文章生成が進化を遂げたことによって、Webライターという職業は”人間だけのもの”ではなくなりました。クラウドソーシングサービスのWebライター募集率も明確に減少傾向にあります。
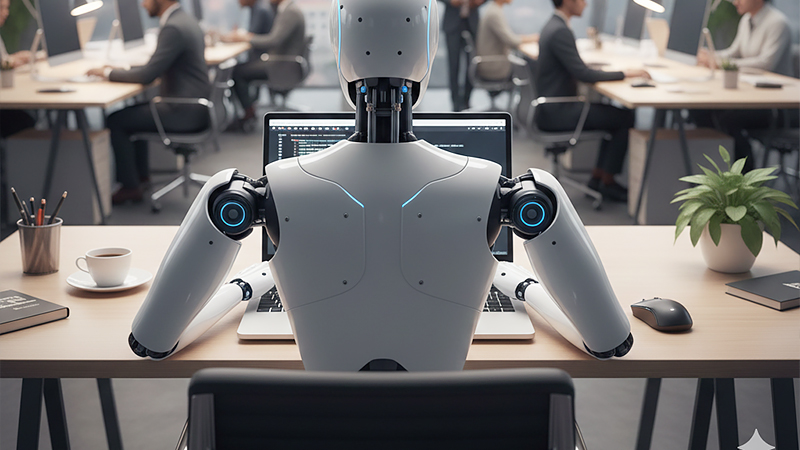
今回は、そんなWebライターの”未来”がテーマです。「AIはWebライターになれるか?」「人間のWebライターの問題点」「未来のWebライターのあり方」について、AIと一緒に考察していきます。

それでは早速見ていきましょう!
「AIはWebライターになれるか?」「人間のWebライターの問題点」「未来のWebライターのあり方」をAIと一緒に考察
AIはWebライターになれるか?

高度な言語モデルを持つAIは、SEOに最適化された記事やブログを迅速かつ正確に生成できます。
「AIはWebライターになれるか?」という疑問に対する答えは「Yes」です。AIは自然な言語と言い回しを用いながら専門的な記事も出力できる上、その出力スピードはタイピングの達人を遥かに上回ります。
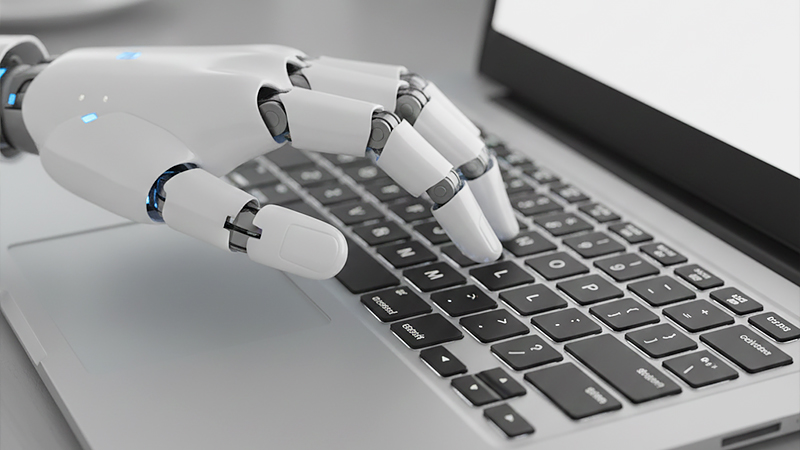
ChatGPT・Gemini・Grokなどの高度な言語モデルのAIは、現在キーワードに基づいて「構造化された記事」を執筆できます。必要とあればWebの情報を参照しながら専門的な記事を出力することも可能です。

画像も生成できるAIは、記事制作の”ワンストップソリューション”になり得ます。現在のAIエージェント機能が進化した場合、さらに精度を高めた”一貫性のある仕事”をするようになっていくでしょう。
AIに記事を書かせる問題点
どんなに進化したように見えても、AIの回答は万全ではなく、時に嘘が盛り込まれることがあります。モデルにもよりますが、何かを引用しているようで「引用元が存在しない」こともあるため、注意が必要です。

こうした問題を回避するためには、執筆を全てAIに任せるのではなく、人間が”ファクトチェック”を行った上で公開することが最も無難です。当然校正に一定の時間を取られますが、記事の精度は高まります。
人間のWebライターの問題点
Webライターは試験を受けずに誰もがなれる職業ですが、クラウドソーシングの隆盛によって「Webライターの母数」が大幅に増え、その結果として低品質な記事と文章が出回るようになりました。

考えられる要因の一つは語彙力と長文構築能力の欠如です。専門トピックを扱う場合には当然”知識と知見”も要求されますが、低品質な記事を分析すると、語彙力と長文構築能力が圧倒的に欠けています。

現在は企業サイトからニュースサイトに至るまで、様々なメディアの多くで低品質な記事と文章を見かけます。誤字脱字も非常に多く、Webライターと編集者の”質の低下”は非常に顕著です。
高品質なWeb記事に必要なこと
記事を書く場合は長文構築能力が必要で、日本語の場合”同じ表現の繰り返し”にならない語彙力も必須です。出来上がった記事を校正する編集者も必須ですが、時間をかければ個人でも校正できます。

SNSのツイートとは異なり、Web媒体に発表した記事はネット上に長く残ります。発表・納品前に記事を読み返して不自然な点や誤りを発見する振り返り作業は、「良質な記事と文章」に繋がるはずです。

AIが書いても人間が書いても、最終チェックは非常に大切ですね。
未来のWebライターのあり方
文章作成で「人間がAIに勝る」部分

人間のWebライターの「独自性と体験」を踏まえた深い洞察、感情を込めたライティング、読者の共感を生むストーリーテリング要素は、AIにはまだ難しい領域です。
AIに書けないのは、文化的なニュアンスや感情・感覚を含んだ文章です。AIには現実世界での体験が存在しないため、これらを文章化できるのは人間しかいません。これがAIに勝る唯一の要素と言えます。

AIには出来ない「体験」は、人間だけの特権です。人生における様々な体験を”知識”として記憶しながら、記事で体験と感じ方を適切に言語化できる人は、未来でもWebライターとして輝くでしょう。

実体験と感情を込めた文章は、いつの時代も輝きを放ちます。
未来の検索エンジンは「人間らしさ」を高評価する
自分だけの経験を文章化すると、記事の価値は大いに高まります。SEOでアルゴリズムを働かせている検索エンジンにも感情や個性は存在しませんが、”著者の独自性”は高く評価されるポイントです。

AI本人は、未来の検索エンジンは書き手の感情や個性が宿るコンテンツを評価すると未来予測しており、それは希少価値を持つからだと分析します。人間らしい記事はAI生成記事との差別化を図れるでしょう。

「人間らしさ」を文章にできるのは人間だけです。
まとめ
AIにはWebライターになれる能力が十分備わっており、人間以上のスピードで文章を生成できます。また人間が記事を執筆する場合も”たたき台”や”構成案”を提案するため、協力者としても便利な存在です。

私はAIとの対話を元に記事を執筆していますが、今後は人間とAIが同じ仕事に取り組むスタンスが加速していくような気がしています。協業することで”お互いの不備を補う共創関係”を築けるからです。
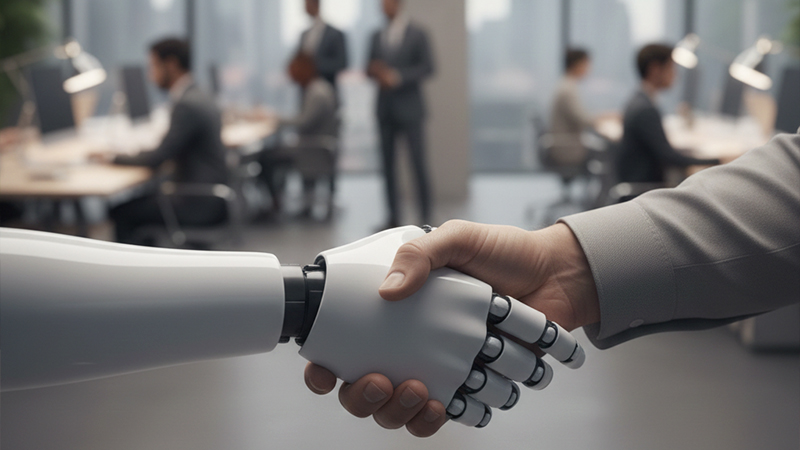
これはWebライターに限ったことではなく、AIが代替できる「全ての職業」に当てはまると思います。AIが徐々に社会へと浸透している今、私たちは”新たな職業の在り方”を考える必要がありそうです。

最後までお読み頂き、ありがとうございました!

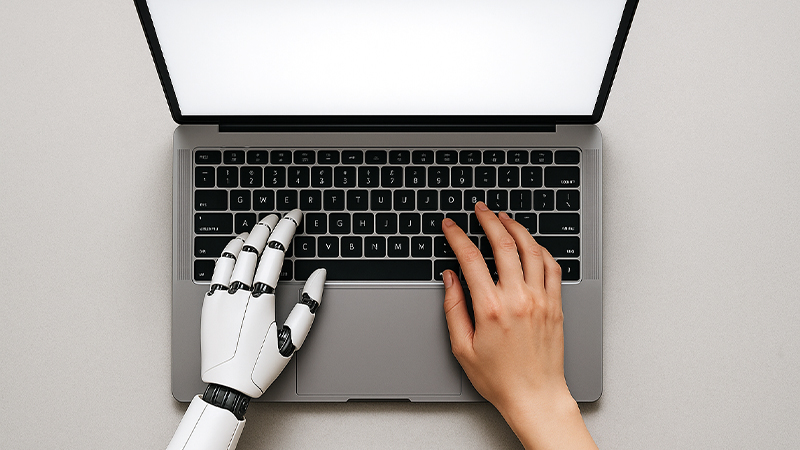


コメント