
SNSの問題と改善しない理由を教えて下さい。

分かりました。過去のSNS問題を取り上げ、改善しない理由も見ていきましょう。
今回のテーマは「SNSの問題」です。実際にSNSが引き金となって発生した問題とSNSの課題を見ながら、主要SNSで問題が改善していない理由についても、AIと一緒に考察していきます。


それでは早速見ていきましょう!
SNSが引き起こした問題・SNSが改善しない理由をAIと一緒に考察
SNSが引き起こした問題
誤情報とフェイクニュースの拡散
2016年の米国大統領選挙ではTwitterやFacebookでフェイクニュースが拡散し、選挙結果に影響を与えたと指摘されました。アメリカ経済学会の報告資料(外部リンク)でも指摘されています。

またコロナ禍の時期において、YouTubeやTikTokで「ワクチンは不妊を引き起こす」など科学的根拠のない情報が拡散して、世界レベルでワクチンに対する疑心暗鬼を引き起こす結果となりました。

コロナ禍における「マスク着用」についても、反対意見と賛成意見が対立しました。今となっては忘れられがちですが、これもSNSの誤情報を鵜呑みにした人々が巻き起こした混乱と言えます。

SNSで真偽不明の情報が素早く伝達していった結果ですね。
エコーチェンバー現象
誤情報の拡散に関与しているのが、SNSのエコーチェンバー現象です。エコーチェンバーは”意見の同調”を示す言葉で、極端に偏向した意見に囲まれた状態に陥る状態を指しています。

SNSのアルゴリズムはユーザーの好みに合わせた情報やコンテンツを優先表示しますが、この仕組みが同調現象をより一層強化してしまうのです。詳細についてはこの記事を参照ください。

偽情報を見た第三者のユーザーが何となく拡散する「負の連鎖」は、SNS上で良く起こります。2016年のイギリスEU離脱では、エコーチェンバー現象が”国民の健全な意見交換”を阻害しました。

未検証の情報がSNSに氾濫することで起こる最も危険な現象は「社会の分断」です。

情報リテラシーの獲得が必要になりますね。
若者のメンタルヘルスへの影響
公衆衛生専門コミュニティ「RSPH」(外部リンク)は、2017年にYoung Health Movementと共同で発表した調査書内で、SNSを長時間使う若者の32%がメンタルヘルスの悪化を訴えていると報告しました。
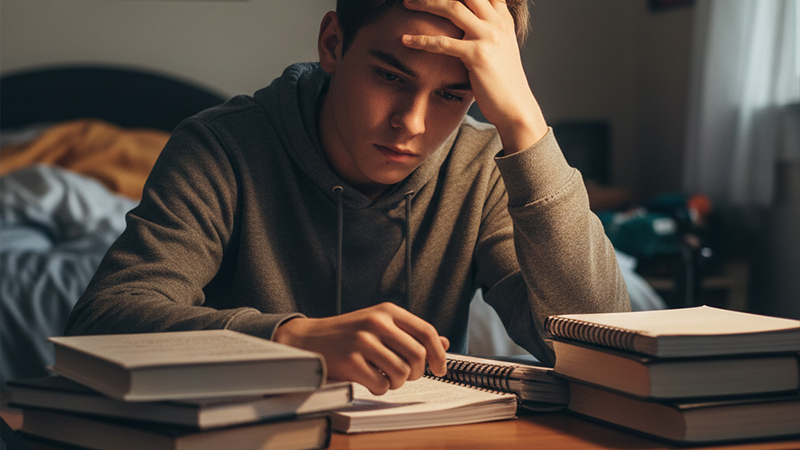
匿名の人物からの”いじめ”もメンタルヘルスに重大な悪影響を及ぼしますが、SNS上に多い虚偽の成功例(例:短期間で稼いだ)等に接し、「自分は成功していない」と思い込む若者が多い点も問題です。
子供を襲う「サイバーブリング」
サイバーブリングはSNS上で不特定のユーザーによる中傷や嫌がらせが24時間続くことで、オーストラリアでは2018年、当時14歳のエイミー・ドリー・エベレットさんが執拗な誹謗中傷が原因で自死しています。

オーストラリアでは2025年12月から、16歳未満の子供によるSNS利用を禁止する法律が施行されました。若者のSNS利用を規制する動きが世界的に高まる中、いち早く法整備に乗り出した事例です。

日本の厚生労働省は、公式HP内に「SNS相談窓口」(外部リンク)を設けており、ページ内に相談できる各団体の連絡先を掲載しています。SNSで困った際には、こうした団体に頼るのも一つの手です。
AI自動生成の悪用問題
SNSにはAI自動生成コンテンツが大量に出回っていますが、本物と見分けがつかないレベルの生成画像や生成動画を生み出して混乱を生み出す事例が後を立たず、利用者のモラルが問題視されています。

自動生成ツールを提供する企業は、「AIに何を事前学習させたのか」を公にしないため、自動生成分野は”ブラックボックス化”しています。この問題は今後も世界レベルで議論を巻き起こしそうです。

ユーザーの利用姿勢も問題になりそうです。
SNSの問題が改善しない理由をAIが考察
SNS投稿者の多くが「再生回数=収益」を求める仕組み(収益化プログラム)が、問題の火に油を注いでいるとAIは洞察します。無責任で過激な投稿ほど、アルゴリズムが好む”視聴維持率”を稼ぎやすい点も問題です。

再生数が収益になるのは「広告」が表示されるためです。運営企業にとって広告収入は生命線で、審査を厳しく取り締まると「損失」が自社に生じるため、あえて”ザルの状態”で審査しているとAIは指摘します。

このため悪質な企業の広告も審査を通過することがあり、その広告で被害者が生まれる構図も維持されています。広告収益維持とユーザー滞在時間確保というビジネス上の優先順位が”安全対策を上回っている”のです。

関心経済(アテンション・エコノミー)の構造的な欠陥が、SNSに負のスパイラルを生み出しています。

有名なSNS全てに当てはまる課題ですね。
まとめ
世界中で毎日利用者を生み出し続けるSNSは、普及に伴い深刻な問題を抱えるようになりました。現在はAI自動生成の使い方も各国で大きく問題視されるようになっています。

急速に発展するテクノロジーは、時に倫理的な課題を置き去りにして成長を続けます。この不備がもたらす悲劇を防ぐために、私たち自身がSNSについて真剣に考えることが必要です。

最後までお読み頂き、ありがとうございました!




コメント